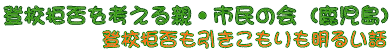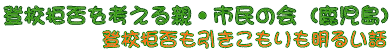|
体験談
2002年7月発行ニュースより。
登校拒否を考える親・市民の会(鹿児島)会報NO.81
登校拒否を考える親・市民の会(鹿児島)では、
毎月の例会の様子をニュースとして、毎月一回発行しています。
その中から毎月3/1から4/1程度をHPに載せています。
体験談(親の会ニュース)目次はこちら
6月例会
1.おかあさんの場合
2.Kさんの場合
3.Hさんの場合
4.Yさんの場合
5.長谷川登紀子さんのお話
私達のホームぺージの掲示板にハンドルネーム「おかあ」という方が"聞いてください"という題で「小学1年生の子が、学校に行かなくなったけど勉強どうしよう」と言ってきたんです。
そしたら私の娘、ハンドルネーム「konan」が、「勉強しなくてもOK」とまた書き込みました。
私の娘は高校時代に友達関係でトラブルがあって不安を抱えて今家にいるんです。
私たち夫婦は登校拒否も、閉じこもりも否定しませんから、私が「娘は閉じこもっているの」と言ったら、すごく怒られました。
娘は「どうして閉じこもりの時だけそういう言葉を使うの?」と言うんです。
私も全くそのとおりだと思ってHPの掲示板に「誰々さんの家は出歩いてばかりいるとは言わないが、閉じこもっているというのは否定的に言うんですね」と書き込みました。
娘はよくインターネットで「あなたは何しているの」と聞かれるので、娘が「家にいてゆっくりしているの」と言うと、「どうして? 仕事は? 大学は?」と言われる、「どうしてそういうことを聞くんだろう。家にいてゆっくりしているのが何が悪いんだろう」ということから始まって、「閉じこもりをしていると思っているあなたに」というメッセージを書きました。
つまり勉強というのはその人がしたいと思う時にするのがいいんです。
それがほんとの勉強なんだと思います。娘を見てつくづく感じます。
なおぶーさんもまた素敵なメッセージを掲示板に寄せてくださいました。(34ページ掲載)
それでは「おかあ」さんに発言してもらいましょう。
Yさん(母):なんで「おかあ」としたのかと言うと、小さい頃子ども達は「お父さん、お母さん」と呼んでいたのですが、ある時から「おとう、おかあ」と言うようになったんです。
私は子どもと近づいた気がしてうれしかったんです。
子どもと対等な感じがして私は好きなんです。
それで長男がメールのネームを「おかあ」にしたらと言ったので、その名前で書きこみました。
書き込みを読んでいただいたらわかると思うのですが、今年の4月から5年生の長男が学校に行かなくなって、この会に参加するのも3回目です。
1回目、2回目は多分暗い顔をしていたと思うんです。
例会では笑いながらその場を過ごしていたような気もしますが、帰ってから落ち込んだり、又登ったりそんなことを繰り返していました。
夫はちょっと型破りな所があって、「いいんじゃない、行かなくても」と言うところがあって、すんなりこの会の考えもスーッと入っていったようでした。
二回目に参加した時は、なおぶーさんや森田さんが「合宿に参加してください。すごく気持ちが変って楽になりますよ」と言ってくれたり、会の後も内沢さんと話をしたり、自分でもなんかわからないんですが「これでいいんだ」と思えるようになってきたんです。
それはたぶん、「あなたの気持ちはよくわかるよ。でもね大丈夫だよ。子どもを信じていれば学校に行かなくても本当に大丈夫だよ」と、言ってくれた同年代の子どもさんを持っているUさんや、先輩のU.Yさんなどたくさんのこの会の方達から言っていただき、その辺でずいぶん変わってきたかなと思います。
でもかなりスピーディだから危ないかなとも取られがちですけど(笑い)、でもほんとに落ち着いてきたんです。
書き込みに書いてありますが、小1の二男もこのままでいいのかなと思いながら、私が毎日手をひいて連れて行ったりしていましたが、様子がおかしくなってきて私ももう限界かなと思いました。
後追いがひどくなったり、学校でチック症状が出ていますと言われたり、イスに座れず下にゴロンとしていますと言われたら、私もそこまでして学校に行かせる必要があるのかなと思っていました。
二男が涙を浮かべて「お母さん、もう行きたくない」と訴えて来たので「行かなくていいよ」とは言ったんですが、「お母さん、僕勉強嫌いなの。勉強ずっとしなくていいの」と言ってきた時に、「う、う〜ん」とうなずいたんですが(笑い)、よかったのかなというのがあるんです。これから人生がある子に「しなくていいんだよ」と親が断言してもいいのかなと思って書き込みました。
Konanさんとなおぶーさんの文を読んで、夫と一緒に「いいんだよね!これで」と言い、no problem! 問題なしと今日はなおさらすっきりしてこの会に参加しました。(笑い)
Kさん:中1男の子です。中学の入学の時点で学校へ「行くのは無理ですから」と縁を切っていますので、学校との関係はありません。
これからもないと思います。
ただ行かなくなって2年になりまして、親の自分自身も不安を持っていますから、早く逞しいお父さんになりたいとこの会に来ています。
少しずつ少しずつ見えてきたかなという感じです。
親の会は明るくて力づけられることもありますし、HPのなおぶーさんの書き込みもよく開いていますが、非常に勉強させられることが多いです。
最初参加したときは、内沢さんの言われることは禅問答みたいに聞こえ、反語に聞こえたんです。
何であんなこと言われるのかさっぱり分かりませんでしたが、その辺が徐々に分かってきました。
―――どんな禅問答に聞こえましたか?
最初は明るい登校拒否というイメージで、登校拒否はすばらしいという発想で、質問される方にも「あなたの子どもさんは登校拒否したほうがいいよ」という感じに聞こえました。
私は「それはちょっと違うんじゃないの」という感じでいて、いろんな経過をたどりながら結局は自己否定がなくなっていく上でそれが大事なんだと理解はするのですが、実際不登校の子の親になってみて、その言葉をバーンと叩きつけられたとき、うーんと考えちゃうんですね。
―――叩きつけられて、考えちゃったのに会に通っているのは何故ですか?
やっぱり、本当かなと。
期待を持たせるのではなく、1番根っこのところで本当の所を言っているということが分かるので。
内沢さんが本音のところをどんどんこっちへぶつけてきますから、逆にそのことについて自分をごまかす必要がないですから、この会は惹かれます。
―――あなたも他の方のお話に皆さんと一緒に笑っているよ。(笑い)
理屈としては分かるんですね。
他人のお子さんのことはよく分かります(笑い)。
そりゃ、行かないほうがいいよとかね(笑い)、思うんですけど、いざ自分の子どもになって、学校に行かないのは自分も納得しているんですけど・・。
例えば前の方と同じで動かない方がいいと、同じことを思っているんですね。(笑い)
今、せっかく自主的に本人が休んでいて、親子というのではなく一人の共同生活者として見ようと努力しているのですから、そういう形として見れば、余計なおせっかいだと少しずつですが理解できるようになりました。
私は福祉関係の仕事をしています。
情短施設は社会福祉法人がやっていると思うんですが、施設というのはある意味では隔離してしまおうという発想なんですね。
戦後からの学校と全く同じで、世の中に合わない人をどこかに隔離して、それで社会的な対面を通そうとする施設なんです。
情短施設の中でいろいろ短期治療施設とあっても、その中に入ってる子どもたちが立派なカウンセラーがいるとかいうことよりも、その施設に行ったということを自分の人生の中でどう捉えるかということ、肯定的に捉えられるかということができるかというと、それは無理でしょうねという感じがします。
それは他の施設も一緒です。身体障害者の施設も、知的障害の施設も一緒ですね。
自分たちがやっている登校拒否の会は、自分の家族としての形態でやっていきましょうというのが基本ですよね。
私は障害を持っている人たちと付き合っていて基本的にそうだなと思うんですね。
「家庭在宅でやろうよ、お父さん、お母さん」と他人には言っているんですけどね。
施設というところはやっぱり押し付けるんですね。
働かない人はだめだからそういう場を設けるとか、入浴、食事などの身辺処理ができないから介助するわけですが、そういうことまで習得するように押し付けるんですね。
前にも出てきましたが、五味太郎さんが「どんな障害を持っていようが、楽チンでいける社会を作ったらどうか」と言っていまして、本当はそうなんだと思いますが、高度な教育が進めば進むほど、認められる社会が作られて当然なのに、逆にどんどん狭められている。
文化や文明が進むほど人間の生き方が窮屈になってきているということが、実感として分かります。障害者や子どもたちが、自分たちの権利を認められるのが当たり前なのにと思います。
―――だんだんとお父さんは禅問答に聞こえなくなったと。(はい、よく理解できます)
Mさんにいろんな会を回ったときのことをお聞きしたことがありましたが、ある会では10回3万円、1回3千円で親の会話を訓練するというのです。
親役、子役になり会話の練習をして、親の訓練をするんだそうです。
人間というのは会話や訓練ではありませんね!
魂をもっています。人間の尊厳はどんな小さい子でも持っています。
会話で不登校を矯正したり直したりする。
一方ではそういう病理があって矯正したり直したりする。
そういうことではないです。
登校拒否という子どもの意思表示に対して、おっしゃったように、人間としてどれだけその子を尊厳するか、尊重するか、きちんと受け入れるかということなんですね。
それは会話の練習や、強制や治療の対象ではないんです。
そのことが最初は禅問答でも少しずつ丁寧に分かっていくのは、なんと言っても体験者の話以外にはないと思います。
今言われたように、他人の話は良く分かるんですね。
自分のことは分からなくても人の話は良く分かるというところから、解きほぐしていく過程が大事ではないかと思っています。
Hさん:18歳の息子です。
私は親の会を楽しみにしているのですが、今日はちょっとしんどいことがありやっとの思いで出席しました。
息子は幼稚園の時から行き渋りがあり、小学校の時代も無理して登校させていました。
中学になると不登校の苦しさから家を空けたり、私へ暴力をふるったりといろいろありました。
14才の時家に帰ってこなくなり、保護願いを出していたら警察から連絡がありました。
私がかけつけてみると、モヒカン刈りで暴れていました。
その時民生委員から児童相談所経由で教護院に預けたら更正するからと強く勧められました。
私はそれまでは、内沢さんとよく連絡を取っていたのですが、いちばん辛い時には連絡もせずひとりで悩んでいました。
この親の会はズバッとはっきり言う会でしたし、親には1ばん辛い会ですよね。
こんなことを言うと初めて参加された方は、よそうかと思われるかもしれませんね。(笑い)
「そんな所へ預けたらいけない」と内沢さんに言われるのは、わかっていましたので、私は自分の辛さから「この子さえいなければ、自分は楽になれる」と思ってしまい、民生委員の話にのっかってしまったのです。
息子は児童相談所へ送られ、そこでも強制的にモヒカン刈りを刈られて丸刈りにされてしまったものですから、暴れてしまって、少年鑑別所へ何の罪名もないのに最高の4週間入れられてしまったのです。
その時のつけがずっとついてまわって、いろいろありました。
4年経って最近やっと息子と話が出来るようになったのです。
又、観察所から電話がありました。
母親の私ではなく、息子と話したいということでした。
息子は今、保護観察処分になっており、定期的に保護司と面談しないといけないのですが、会いたがらないのでなかなか処分が終わりません。
その後、息子は暴走族にも入ったりしていろいろあったものですから、保護観察処分が20才までとなったのです。
監察所から、もし本人が出頭しなければ逮捕するということと、家裁に差し戻して1から又始めますということでした。
どうしてこんな大げさなことになるのかなあと思ってしまいます。
電話で話しても分かってもらえそうになかったので、「息子には伝えておきます」と言って切りました。
以前、監察官と話した時、「まあ、2週間ぐらいは待ちましょう。その間に保護司の方に連絡を取ったよい」と言われました。その後、息子は街でバッタリ保護司と会ったのです。
保護司の先生は「ここで会ったからしばらく来なくていいですよ」といいました。
しかし、監察官はそれは偶然だからカウントされないので、とにかく自分の足で保護司の所へ行きなさいととりあってくれないのです(笑い)。
私としては「何のための法律なのか?」と思います。
子どもの状態がよくなるために法律はあるべきなのに、ただ形式的に保護司と会うことのみを言い立てるのが納得できません。
そこで私自身が落ち込んで孤独になってしまいました。
内沢さんに電話したら「鑑別所に入った時のことを息子さんに謝りなさい」と言われました。
私は息子に「今日は謝ろう、今日は謝ろう」と思っていたのですが、お互いすれ違いだったり、なんとなく息子が不機嫌そうにしていると機会を逃してしまって(笑い)、まだ謝っていないのです。
どうしようかなと思って、そのときの事を手紙に書いて謝りました。
「あの時のお母さんは本当に弱くてダメな母親だったね。しかし、今はお母さんは強くなりどんなことがあってもアナタを守るお母さんになるからね。あの時はアナタを手放して本当にごめんなさいね」と。
息子はその手紙を読んだのか聞くのも怖くて、分からないのですが。手紙が少し動いているので読んだのではないかと思っています。(笑い)
本当に情けない親でまだまだだと思っています。
―――手紙を書いただけでも大きな前進じゃないですか。
息子と話していたときのことです。
「お母さんは6月いっぱいで今の仕事を止めて、失業給付金を受けながら、次の仕事の資格を取ろうとやっているので、アナタもそんな仕事があるかもよ」と言ったら、だんだん不機嫌になり、その時ご飯のお代わりがなかったら、なお機嫌が悪くなり、電気釜を蹴って、電気釜が壊れてしまいました。(笑い)
息子は中2の頃、騎手になりたかったのです。
学校へ行っていなかったので何かにならなくてはと思っていたみたいでしたし、馬が大好きでしたから。
最近騎手になっていたらよかったなあと言うものですから、「今からでもなればいいがね」と言ったら、「もう18才だから遅い」と言いました。私が言っても言ってもダメなんです。
―――そんなこと言うからよ(笑い)。親だから何か言わないといけないと思うからうまくしゃべれないと言う先ほどのお話は分かりますか? (はい、分かります)
一緒に寄り添って住んでいる人間同士、息子さんからいっぱいエネルギーをもらったよね。(はい) そんな気持ちに感謝して住んでいけば、息子さんの気持ちが分かってくると思いますよ。
あんまり親として何かを言わないとと考えると、気持ちは余り伝わらないんですよね。(はい)
―――内沢達:大事なことは、どんなことあってもそれを受けとめるかどうかです。
逮捕されることはまずないのですが、たとえ逮捕されることになっても、我が子だから全部受けとめようということです。
学校へ行っていないときは将来どうなるんだろうかと心配し、今は、警察に逮捕されたら、また息子さんが傷つきどうなるんだろうかと心配している訳ですね。(はい)
そういうことにはならないけれど、なったらなったで息子さんに、それを受けとめてもらわないといけません。そのときはお母さんが力になるということです。
こうしたことはHさんだけの問題ではなくて、先ほどの初めて参加されたYさんの話にも当てはまります。
じつはYさんと息子さんの関係はとてもいい状態なんですよ。
Yさんのお父さんは、お母さんに「どうして息子とコミュニュケーションがとれないの?」とおっしゃったそうですが、はるかにお母さんの方がお父さんより息子さんとコミュニュケーションがとれています。
Hさんは、ついつい励ましのつもりで息子さんにハローワークのこととか言ってしまいました。
息子さんはそんなことは嫌いますよ。
自己否定があるところに自分が一番気にしていることを確認させられるわけでしょう。
だから、電気釜を蹴飛ばすのはいけないことだけど、息子さんの立場にたてば、さもありなんです。
保護司さんとの関わり方も、お母さんが関わるのではなく、息子さん自身にやってもらわないといけない。
行かないことで息子さんが不利益をこうむったとしても、それは息子さん自身に受けとめてもらわなければいけません。
先日、僕は山口愛美ちゃんとチャットしたんです。「愛美ちゃん、どうだった?」(「よかったよ」と返事。笑い)。そのチャットの中で、愛美ちゃんが、「私、元気になってきているけど、まだ自己否定しているんだよねえ」と自己否定している自分がだめみたいなことを言ったものだから、僕は「自己否定している自分を否定することがよくない。もっと自己否定したらいい」と言ったのです。
自分をダメだダメだと思っているときは、辛くて大変だけど、親であっても代わってあげられません。
本人が辛さ、苦しさを受けとめるしかない。
お父さんお母さんはそばに居てあげるだけで十分です。
何も言わなくてかまいません。お父さんの山口良治さんは愛美ちゃんに言っていないけど、本人がダメだと思っているときに、「君は大丈夫だ、大丈夫だ」と言っても何の慰めにもなりません。
2、3年前、Hさんはもっともっと大変だったんです。
今はそのとき以上に大変なことはないのだし、あったとしても、それを受けとめるべきです。
その大変さはまず最初に息子さん自身に受けとめてもらうべきです。
言葉でいろいろ言ってもダメなんです。
そんなときは本人に耐えてもらうしかありません。
余計なことは言わないことですね。
何故、余計なことを親はつい言ってしまうかというと、子どもの問題としてとらえているからなんですよ。
今日初めて参加された方には分かりにくいと思いますが、学校へ行かないのは子どもだから、登校拒否は子どもの問題だと思われがちですが、そうではありません。
この親の会は登校拒否を否定的に見ません。
再登校するようになることが必ずしもいいことではありませんが、行くようになるためにも、ズバリゆっくり休んでもらった方がいいですね。
「さみだれ登校」するより、そのほうがいいですね。
中3のとき思い切って休んで高校から行けるようになった例もあります。
そういうとまた、期待する人がいるかもしれませんが(笑い)、無理して行ったり行かなかったりすると、両親がバックアップしてくれているのに、僕はまた行けなかったとなおさら自信をなくし自己否定を強めていくので、ゆっくり休んでもらうに限ります。
不登校、登校拒否というのは別にたいした問題ではありません。
私たちの会は子どものことをきっかけとして親が集まり13年やってきましたが、問われているのは子どもではなく、大人、親の考え方、生き方なんだと分かってきました。
私たちは、不登校の子どもたちから実に多くのことを学んできました。
1冊の本を紹介します。「笑う不登校」という本です(教育史料出版会、1999年)。
不登校のお子さんを持つ親御さん20人が本の副題「子どもと楽しむそれぞれの日々」にあるように、それぞれの体験や思いをつづっています。
僕たちは親の会をやって、何を学んできたかというと、その大きなひとつは子どもだけでなく我々大人もゆっくりしていいんだということです。
わが子の不登校と出会って、親の会に足を運びながら、はたと、われわれ大人もあくせくと働いてばかりでなかったのかと気づいたんです。
子どもだけでなく、われわれ大人も辛い時や大変な時はゆっくり休んでいいのだと分かったんです。
学校に行かせることだけを考えているようでは、学校が主人公になっていて、子どもやわれわれ大人が主人公でなくなっているのではないかと考えるようになりました。
「会社人間」の場合、会社の都合にばかり自分を合わせていて、自分が自分の人生の主人公になっていません。
わが子の不登校のことを考えるときも、自分は理解しているつもりだけれども、祖父母がとか、親戚がとか、世間がとか、まわりを気遣ってばかりで、さっぱり自分が主人公になっていません。
もっと自分の考え方を大切にして、われわれ大人も自分のペースで生きていったらいいんだと学んできました。
「笑う不登校」の前書きには、「私たちは、学校に行かずに家を中心に過ごしている我が子とともに暮らしている」「要は自分たちにあった生き方をしていけばいいんだ」「子どもを大人になるための通過地点としてとらえない」「あまり未来を思い煩うことなく、今、子どもと共にいることを大事にして暮らしている」「今を大事にすることは、将来どんなことに出会っても、その今を自分で受けとめていける心が育っていることだと思う」などとあります。
普通の親御さんたちがまとめたとてもイイ本です。
子どもが学校に行かないと将来が心配だと思う人が少なくありませんが、この本は「今を大切にしよう」と。
今、家で子どもといっしょに楽しく生活しようと言っています。
今を大事にして、その時々の今を積み重ねていったら、子どもたちが必ず出会う将来の「今」にもしっかりと関わっていけるのだと思います。
僕の話は少し抽象的ですけど、また皆さんで交流してください。
Yさん:もうすぐ18才になります。
今日久し振りに参加しました。
小学5年から不登校です。
不登校になった時、母はパニックになり鹿大の心療内科へ私を連れて行きました。
そこでは「アナタは人と話すのが苦手だから、しばらく通って話す訓練をしなさい」と言われました。
病院で全く知らない人とグループになって話すというものです。
その時に母がこの親の会と出会って、私は心療内科へ行かずにすみました。
知らない人と会うのも嫌だったし、話もしたくなかったのでいくら鹿大の先生に「対人恐怖症だから」と言われても、行きたくはなかったですが、先生の前や母の前で行きたくないとは言えませんでした。
―――どうしてお母さんに病院には行きたくないと言えなかったか教えて下さい。
自分が悪いと思っていたし、「対人恐怖症」という病気だったんだなあと思って納得したら、行かないといけないのかなあと思ってしまいました。
母が親の会に出会った後、その頃は兄も不登校になっていて、兄と二人で母に呼ばれて「学校へ行かなくていいよ」と、いきなり言われてびっくりしました。
それまでは「学校へ行け行け」という感じでしたから(笑い)。
朝私は行きたくないから、おなかが痛いと言って逃げまわっていると、母が「学校へ行きなさい」と泣きながら言って、私を家から追い立てました。
その頃は夜ひとりで眠れなくて、夜が怖くて両親の部屋へこっそりと忍び込んで寝たこともありました。母が「わあ、びっくりした」と言いましたが、追い出さずに一緒に寝てくれました。
でも夜中に目が覚めると台所の方で、父と母が話しているのが聞こえてきて、それが悲しいでした。
―――どんなお話をしていたの?
どうして学校に行かないのだろうか。
自分の育て方が悪かったんだろうかと母は自分を責めていましたので、父は母を慰めて、母は泣いていました。
その姿をみて「ああ、どうしたらいいんだろう・・。でも私は学校へは行けないし」と思って・・。
―――じゃ、お家にいても遠慮しているところがあったのね。
そうですね。母はパートに出ていたので、昼間はひとりでした。
あとで兄も不登校になるんですが、その頃は学校に行っていましたから。
―――お家にいてもゆっくり出来ない状態でしたね。(はい)
じゃ、お母さんが学校へ行かなくていいよと言ってくれた時の気持ちはどうでしたか?
もう、びっくりしましたがホッとして泣いてしまいました。
力が抜けたというか。
そのときはみんなして泣きました(笑い)。
ああ、行かなくていいんだと思って。そのときまで1年ぐらい経っていましたから。
―――中学はどうしましたか?
1日も行きませんでした。
卒業式の時、校長先生から「これまで習った事を生かして、生きて行きなさい」と言われました(笑い)。
1日も行っていないのに、「「ハイ、頑張ります」と言いました(笑い)。
通信高校に行ったのですが、1、2回行ってあわないなと思って止めました。
―――自分から行きたいと思ったの?
はい、3年ぐらい家にばかりいたので、そろそろ外へ出てみようかな、何か変わるかもと思って入学しましたが、やっぱり行けなくて。受け付けなかったので。
―――お父さん、お母さんは何も言いませんでしたか?
はい、言いませんでした。
しかし小学校の頃は微妙に不安がっていました。(笑い)
―――お母さんがYさんに謝ったのは何年ぐらい前ですか。
そのお話を聞いて私は自分が泣いたのを覚えています。
4年ぐらい前かもしれません。
その後は不登校についてあまり母とは話していません。
―――今学校へ行かなくてよかったと思っていますか?
はい、そう思っています。
行っていたら、今の自分は絶対無いと思うし、どこか壊れていたかもしれないし、家族の関係とか。今の状態は無いと思います。
―――今、自分らしく生きている感じを実感しているのね。
(はい) Yさんは学校に行かないからといって、自分を追い詰めた事はなかったの?
最初の頃は、人の目が怖かったりしました。
自分が学校に行っていないことが他の子と違うので、道を歩いていても、同級生とか出会うと「あの子、学校へ行っていない子だよ」と言われそうで怖かったです。
人のうわさが怖くて他人と一緒にいるのがいやでした。
―――ご両親は何も言わなくなったけど、同居なさっているお祖母ちゃんが、いろいろとおっしゃった事は覚えていますか?
そうですね。
今でもたまに言うんです。「今でも納得してないわよ」と。(笑い)
―――Yさんが行かなくなって6年経つけど、お祖母ちゃんはまだあきらめきれないのですか?
(母):結局祖母には祖母の世界あるので、祖母のお友達には孫が不登校だというのを知られたくないのです。
今だにそれはずっと一貫しています。
同じ家に上と下に住んでいます。
祖母のお友達も近所にいるのです。
だから○○さんと、○○さんにだけは知られたくないというのです。(もう、みんな知っていますよ。笑い)
私と同世代では、みんな知っているのですが、祖母の世代には、まだ知られていません。
とにかく自分の生活を守りたいと祖母は思っていますので、祖母の気持ちも汲んであげないといけませんので、親としては学校へ行かないのは何ともないけど、お祖母ちゃんのお友達が来た時には2階へは行かないようにと、ごめんねと言いつつ頼んでいます(笑い)。
2世帯で住む大変さもあります。
子ども達にはすまないと思いますけどね。
この会を知る前にはいろんな所にへ子どもを連れまわして、私が不安で不安で、この子たちをどう育てたらいいのか分からなくて・・・。
結局あちこち連れまわしても「これでいいんだよ」という確実な答えはどこからももらえなかったです。
結局、「家族が悪い、親の育て方が悪い、この子が悪い」と散々言われると、私も胸を張って外出できないし、子どもも外へ出せないと落ち込み、自信を失いました。
その時この会の8周年の集いに出会って、初めて「行かなくていいんだよ」と言われて、そのひと言ですごく救われました。そのひと言がなければ、今だに娘の手を引いて学校に行っていたんじゃないかと思います。(笑い)
私の両親からも周りからも、どこへ行っても「学校へ行かない子を何故育てたんだ、行けない子はダメなんだ」と責められて、もう私も子どももパニックなり、その頃この会を知り「学校に行かなくても生きていける」ということを知り、すごくホッとしました。
―――数日前、私はデパートでYさんとお母さんが姉妹のように仲良く買い物をしていらっしゃるのに出会いました。「今日は休みなんです」とおっしゃるお母さんに、Yさんが「私は毎日休みです」と言ったのね。(笑い)
息子さんは今、家にいるのですね。
(母):はい、19歳です。
来年成人になります。
息子は「僕は20才になっても現状を抜けだせない」と言っています。
息子も2、3回通信制へ通ったのですが、今はもちろん行っていません。
今、サックスを始めています。
ちょっとやる気が出てきたのかなあと思って。(笑い)
(お母さん、娘さんから学んだらいいね)(笑い)。
私の傍で、息子は意識しているのかしていないのか分かりませんが、アルバイト情報誌を広げてみたり、ストアに行った時も情報誌を買って「いいのかなあ」なんて言います。
―――そんときお母さんはなんて言うの? (「今のままでいいじゃないの。何もしなくて」と言うのです。) 心の奥底では将来どうなると思いながらですか?
やっぱり、少しあります。この「笑う不登校」の前文を読んで、またしっかりと再確認しました。
ここに来ると「今が大事。」と思うんだけど、息子を見ると将来は、と思う自分もいます。
―――きっと息子さんもアッと思う間にいなくなるかも知れません。
今の幸せを大切に、今を生きるということが大事ですね。
―――最後に長谷川さんに話していただきましょう。この親の会の創立を呼びかけて14年間、会に毎回こられています。
長谷川登喜子さん:久しぶりにお話できるチャンスをいただきました。(笑い)
息子は現在22才です。
息子は小学校3年から中学校卒業するまでの6年間1日も学校に行かずに過ごしました。
不登校になったはじめの頃は皆さんがおっしゃっていたように、学校からの電話にも応えて、あの手、この手でなんとか学校に行かせようとしていました。
しかし3ヶ月経つと子どもは人形のように表情をなくしました。
それを見て私は学校よりもわが子の命を守ろうと思って、学校と決別したんです。
今日は皆さんの話を聞いていて、中3だからとか、高校だからとか、学校の年令に縛られているんじゃないかと思いました。
私は学校を休ませた時からそういうことを全部排除したんです。
この子がしあわせで笑顔があったらいいと思いました。
学校からのプレッシャーがあった時は子どもの顔色が悪くなり、隠れたりしましたから、学校に出向き校長や担任に子どもが学校を休んでもなんの問題もないことを話し、学校の盾となって子どもを守りました。
おかげで中学校になった時にはクラスも担任も知らされずに過ごしたんですが、それがとても楽で幸せに生活することができました。
家での過ごし方も子どもにとって24時間あるわけです。
親があれをしなさい、これをしなさいと言わなくなった時に初めて子どもの自由な時間というのができるわけです。
はじめは子どももどうしたらいいかがわからなくて、のたうちまわって、それでも親はじっと見ているしかない、これは子どもがやっていくことなんだということで口出ししませんでした。
逆にそういう苦しさを経験しました。
でも子どもがあれをしたい、これをしたいと言ってきたときには真正面から話をして受け止めてやりました。
親がゆっくり生活しているとだんだん子どもが楽しいことを言ってくるんです。
わー、こんなことを感じるんだ、こんな言葉の使い方があるんだと新しい発見がたくさんありました。
私はその言葉を書き留めていなかったことを今とても残念に思っています。
子どもが学校に行かないなんて自分でも全然考えられなかったことなので、同じ悩みを持つ人たちと一緒に支え合っていけたらと思ってこの会を呼びかけたのが、14年前です。
この会に来てエネルギーをもらって帰って下さい。
この私が大丈夫だったんですから、皆さん大丈夫です。
今日1日を大切にして、その積み重ねの中に幸せがあると思うので、親子で楽しく生活してください。
|