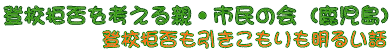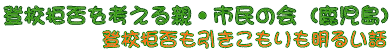|
体験談
2005年12月発行ニュースより。
登校拒否を考える親・市民の会(鹿児島)会報NO.117
登校拒否を考える親・市民の会(鹿児島)では、
毎月の例会の様子をニュースとして、毎月一回発行しています。
その中から毎月2割から3割程度をHPに載せています。
体験談(親の会ニュース)目次はこちら→
1 扉のことばゆく年に愛をこめて、くる年に幸せたくして
2 家族ひとりひとりの人生を大切にするようになって Gさん
3 息子が教えてくれた Mさん
4 家にいる娘たちが支えてくれます Nさん
5 親は子どもを信頼していればいいんだね 内園浩二さん
6 子どもは自分で解決できる力をもっている 内沢 達
ゆく年に愛をこめて、くる年に幸せたくして
2005年がもうすぐ終わろうとしています。今年は、親の会にとって大きな出来事がありました。
かけがえのない仲間である内園由貴代さんが3月に亡くなりました。残されたご家族はもちろんのこと、私たちは深い悲しみに耐えなければなりませんでした。
夫の浩二さんは、「最近気持ちも穏やかになって、・・・家族で支えあっています」とお話されました。いじめで亡くなった村方勝己君のご両親も悲しみに耐え、この9年家族の絆を深めてこられました。
きっと、みなさんのご家族にもたくさんの出来事があったことでしょう。
困難だと思ったり、受けとめられないことだと思ったり、また、子どもたちからの問題提起に戸惑ったり・・・。
でも、それらはいつでも生きるうえで大事なチャンスをあたえてくれるものだと気づかされます(まだ、気づいていない・・・と感じておられる方は、来年は気づくチャンスがあるよね、と希望がわく)。
考え方ひとつで幸せは自分で作るものだとわかります。
夫、内沢達の病気後、私たち夫婦は以前よりいっそう幸せです。
「病気があって大変だったけれど、あれがあったから、こんなにも幸せを感じることができるんだね」という思いです。
困難はひとりぼっちでは解決しません。
親の会で繋がりあって、支えあってこそです。
来年も親の会をなくてはならない存在として大きく育てていきましょう。(内沢朋子)
2 家族ひとりひとりの人生を
大切にするようになって Gさん
(父)私は9月30日で職場を辞めました。
正式に辞めるのは、来年の4月1日付けなんですけど、それまでは休暇扱いです。
今、私は毎日魚釣りに出かけているので、顔も黒くなりました。(笑い)
会社を辞めたときの朝、「ああ、今日から会社へ行かなくていいんだ」と思ったら、肩の荷がおり力が抜けていくのを感じました。
最初の1ヶ月くらいは、とまどいがありました。
今はもう慣れて、毎日図書館通いをしています。
そこで社会保障や社会福祉関係の本を片っ端から読んで、不明な点は社会保険庁や社会福祉事務所、ハローワークや市役所へ出向き質問しています。
―――社会福祉関係へ将来進みたいのですか?
いや、そういうのじゃなくて、自分が辞めたときの退職金とかはわかりますけど、健康保険の切り替えとか、年金とかですね。
全然、分からなかったので、自分のために調べています。
17歳の娘は10月から自主的に塾に行っています。
娘は高1から行かなくなり、私の単身赴任先のさつま川内市の高校へ転入しましたけれど行かず、今年の3月末に退学しました。
娘は高校を辞めて本当に良かったと言っていました。
10月くらいから、大検を受けるために塾へ行きたいと自分から言って通っています。
最近の娘は実に生き生きとして大声でよく笑いますね。
うるさいくらい笑っているし、妻が留守のときも、塾の先生の話とか私によく話しかけてきますので、私もとってもうれしいです。(笑い)
料理も作ってくれて変わってきましたね。娘が元気になってくれてほんとうにありがたいです。
―――会社を辞められて楽になりましたか?
本当に楽になりました。
最初は夢の中にも「今日はこの仕事をしなくてはいけない」と出てきていましたけど、今はもう、それもなく本当に楽になりました。
焦る気もなくホッとしています。私はこう見えても今、51歳です。(笑い)
60歳で辞めるか、55歳で辞めるか、51歳で辞めるか、色々悩みましたけど、ある程度、体力も気力も残っている51歳で辞めて良かったと思っています。
まあ、今後は分かりませんけどね。(笑い)
―――じゃあ、娘さんにも嫌われなくなった?
以前は付き合いで飲み方も多く、毎晩遅く帰りまして、金曜日ともなると午前様で、娘からも嫌われて、自分でも「オレはアル中かな」と思っていましたけど、会社を辞めてからは一滴も飲まなくても平気ですね(笑い)。
「アル中ではなかったなあ」とホッと安心しました(笑い)。
酒を止めたら体重も減ってきてよかったです。
(母)私は、娘が学校へ行っていないとき、よくひとりで外出していました。
行っていない娘を見るとつい何か言いそうな自分が嫌だったし、娘と二人でいると、空気が重いというか、何かしたらとかいろんなことを言いそうでしたので、その頃は図書館へ通っていました。
初めの頃は夜も眠れなくなっていきました。本を読んだり、親の会へ参加したりするなかで、まあいいかと少しずつ思えるようになりました。
娘も3月末で退学してから家でゆっくりしていたのですが、娘は京都で生まれたものですから、「京都へ行ってみたい」と言い出し、行くことになりました。
娘は1ヶ月くらいかけて自分の行きたいところを調べて、8月に10日間くらい二人で旅してきました。京都へ行ったら後で何かをしてくれそうとか全然そういうことは思わなくて、「まあ、明日のことは分からないので、今日が楽しければいいかな」くらいの気持ちでした。
旅行中は、お互いに疲れてしまってケンカしたり(笑い)、ここまで言ったらダメかなと思いつつも、ついつい言いあって(笑い)。
最後の2日間は、娘が「お母さん、お互いに自由行動しよう」と言ったので、別々に行動しました(笑い)。
帰ってきてから娘は「とっても楽しかった。京都の人は皆優しかった」と楽しそうでした。
旅から帰ってきたら、「夕飯は私が作ってみる」と言って作りだしました。
それから娘は「私、大学に行ってみたいなあ」と言い出しましたので、「お母さんは何もしてあげられないよ」と言うと、娘は鹿児島市内の大検専門の予備校へ自分で電話していました。
しかし自分には合わないかなあと言って、さつま川内市の塾へ行きましたら、「お母さんもいらしてください」と言われたので、私も行きました。
教師も鹿大の学生さんなので、年齢も近くてとても楽しいようです。
「今日はこんなことを話したよ」と言ってますので、それだけでもいいのかなと思っています。
―――ご家庭の中が、今、すごく穏やかでしょう。
はい、そうですね。
夫が会社を辞めるときは、これから先どうなるかなと思っていましたけど、映画を観に行ったり、図書館へ通って調べ物をしたり、市の広報を見て、いろんなものに参加するために出かけたりと、ほとんど家にいず出歩いていますので安心しました。
釣りに行って友達もできて、お互い名前は知らないけれど、夫は「おじさん、おじさん」と呼ばれて(笑い)、色々教えてもらって楽しそうです。
娘も夫も楽しそうですので、私も仕事をしようと思っています。
仕事の研修会もあるので、今、週の半分は実家に帰っています。
私の友人とは、子どもを抜きにした話のできる人なので、「これからの後半の人生を私も頑張って楽しまなくちゃ」と思い、刺激を受けています。
(父)ただひとつ残念なことがありました。
妻と娘が8月に京都へ旅行したんですけど、私も10月からだったら自由の身ですので、一緒に行けたんですよ。(大笑い)
一番忙しいときでした。あと少し僕を待ってくれたら良かったんです。(笑い)
―――最初に、私の家を訪ねてこられた時の大変さを思うと、今考えられないくらいですね。
今はすごくお幸せになられてね。
考え方ひとつで幸せは自分で作っていくことができるんですね。よかったですね。
3 息子が教えてくれた Mさん
18歳の息子です。
中3の2学期から不登校になりました。
高校は2日行っただけで行かなくなり、家にいます。
進級の件で、出席日数が足りないし、もう一度1年生をやる気持ちもなかったので、退学しました。
現在はテレビゲームなどをやって楽しくやっています。妻も月の半分はパートに行ってますので、息子は台所に立って自分の食事の支度もやっています。
私も息子が中学で行かなくなったとき、高校へ入学したとき、退学したときは、Gさんと一緒で心が揺れ動いていました。
息子が中学で不登校になったとき、最初は「学校へ行かなくていいよ」と言っていましたけれど、できるだけ早くきっかけを作って、波乗りのように学校へ行くタイミングをどうつかまえようか、その波乗りに遅れたらどうしようか、という焦りが私の中にありました。
そういうことで早く学校に行けるタイミングをつかもうと焦っていました。
高校も行ってなくて、高校を退学するかどうかで悩んでいた時、インターネットでこの親の会を知り参加してみました。
そのときの悩みは、学校に行ってなくても形の上では在籍しているので、普通に社会へ出てから「履歴書が作る人生」だけれど、辞めたら将来どうなるんだろうかという不安がありました。
しかし、親の会に参加していく中で、同じような体験をされてる方々が多く、なんら問題がないと分かり、少しずつ私も妻も心が大分落ち着いて、特に妻は落ち着いて、もう参加しなくなりましたけど(笑い)。
しかし、私はまだ「ここからだな」という思いがあるし、最初内沢さんがおっしゃったように「夫婦とは、家族とは何なのか、家族の愛は何なのか」を不登校の息子が私たち夫婦に教えてくれました。
考えるきっかけを与えてくれて、親の会の皆さんの有意義なお話が聞けて、それが私自身にとっても、私の家族にとってもためになることだと思っています。
―――ほんとうにそうですよね。
子どもが教えてくれるものね。
息子さんは落ち着いて家にいて、ご両親も不安がないのですね。
いや、不安がないわけではありません。
私自身も二十歳のころ、学校へ行っていませんでした。
私は小さい頃からきつ音があって、親は「小さい頃はあっても、今は治ってる」と思っていましたが、私の方は恥ずかしいから、そうならないようにしようと思って緊張してきました。
親の気持ちと自分の気持ちがずれてしまって、青春期特有の気持ちも加わって学校へは行かず、ずっと東京の下宿に閉じこもっていました。
そのことを両親に話したら、母親が新聞にきつ音の会があると私に手紙で知らせてくれました。福岡に帰省したときに参加して、その体験が自分というものを築いていったのです。
何か壁にぶち当たったとき、私は出来ないことをいつもきつ音のせいにしていました。
出来ないことがあると、逆に「どもらない完璧な自分」を空想して、きつ音さえなければ自分はこれが出来るのにと、自分の弱さをすべてそのせいにしていたことに気づいたんです。
そういう中で、きつ音でもいいんだ、いろんな人がいるんだと分かっていきました。
完璧な自分を空想していく自分のおかしさにはっきりと自分自身気づかされたんです。
私にきっかけを与えてくれたのは母でした。
例会があることを知らせてくれて「じゃあ、行ってみようか」と私も思って行動しました。
自分は今、息子に○○があるよ、なんて言ってませんけど、私の母が私にしてくれたように親として何か息子にしてあげられることはないのかと常に思います。
例えば、息子を放っておくということの中でも、何かひとつでも私に出来ることを、何かをきっかけにして出来ないものかと常々思います。
―――放っておくというのは、親としてなかなかできるものではありません。
放っておくというのは、息子さんに全幅の信頼をおいているということで初めてできるものですね。
心から「あなたの存在自身がお父さんやあお母さんには大切でかけがえのないものなんだよ、存在自身が価値あるものなんだよ」というメッセージを息子さんに伝えているということですよね。
お母様がそうして伝えて下さったことも、結果はあなたご自身が納得して気がついていかれ楽になったわけでしょう。
息子さんもそういうご両親の姿勢から納得していくんですね。
自分の責任において人生を決めていったことは、ちゃんと自分のものになっていきます。
お母様に教えられて、もしイヤイヤ行って納得されなかったら、それは自分で決めていないから他へ責任を転嫁しがちです。
自分で決めるということがとても大事なんですね。
例えば26歳の私の娘・玲子が3年半閉じこもっていたときに、娘は不安でたまらなくてイライラを私たちにぶつけて親子ケンカもしたけど、私はそんな娘をごく自然なこととして受け止めて、心から愛していったし、また、伝わったから自分のあるがままを受け止められて、飛び立っていったのかなと思っています。
多くの引きこもっている子どもたちは引きこもっていること自体を否定します。
否定的に思ったり、生きている価値がないとか、このままではダメと思ったりします。
そのとき親は何をするかといえば「そのままのあなたが大事なんだよ」と言って、その愛情を惜しみなく与えることだと思うし、それに尽きると思います。
きっとMさんのお母様がそういうふうにされたのは、そのままでいいんだよと伝えてくださったからだと思うし、親のそういう愛情は子どもにとっても私たち親にとっても素晴らしい財産だと思います。
4 家にいる娘たちが支えてくれます Nさん
長女は中学のときから、次女は小5から不登校になり、ずっと家にいます。
今20歳と17歳です。
4月から次々と身内の不幸があり、その後夫の手術、姑の手術と、もうほっとする暇もありませんでした。
娘たちも本当は引きこもっていたかったかもしれないのに、大切な家族なのだからと私と一緒に行動していました。
私は「無理しなくていいんだよ。お父さんとお母さんでするから」と言ったんですけど、「命がかかった大事な手術なんだから、介護はできないけれど自分たちにできることは顔を見せることだから」と言って、よく私を助けてくれました。
姑の手術が終わりほっとしたら、今度は実家の母が頭に動脈瘤が発見され、手術しようかどうしようかで悩みました。
手術したとしてもマイナスのこともあり得るようで、私は一気に気持ちが崩れ落ちました。
今はそのまま様子をみながら日常生活を送っています。
一番よかったのは父が母に対して優しくなったことでしょうか。
―――私達夫婦みたいねえ。(笑い)
娘さんたちはあなたのお手伝いをしたり、病気のお祖母ちゃんのお見舞いに行ったりしているの?
はい。家にいるより病院に行ってお祖母ちゃんの顔を見るほうが安心できるし、自分にできることを手伝うとみんなが喜んでくれると言っていました。
今は私の実家へ週1回出かけて家事を手伝ってくれていて、私も助かりますし、母も喜んでいます。
娘たちがしたいといって動いているので放っておいたらいいのに、私は無理させているんじゃないかと気になったりして、つい「お母さんがやるからいいよ」なんて言ってしまいます。
娘たちのやさしさから出ている行動に、実際私も大いに助かっているんです。
でも娘に甘えすぎていないかと悩んでしまうんです。
―――もっと娘さん達のことを信じましょう。
娘さんが自分の意思でやっていることなので、「ありがとう」「助かるわ」「これもやって」と頼めばいいじゃないですか。それが家族というものです。無理してやっていることか、自然にやっていることかはすぐに分かります。
子どもさんが自分で決めて自然にやっていることが大事ですね。
困ったときには助け合う、子ども達も家族の一員として役に立てることに誇りと喜びを持っていることがよく伝わってきますね。
あなたの夫はお仕事の忙しさはどうですか?
転勤で職場に慣れるまでストレスが溜まっていましたが、川内に単身赴任しているときよりは楽になっています。
夫も自分の手術と自分の母の手術でいろいろあって、支えてくれてはいますけど、どうしても母娘対夫と3対1になることがありますね。(笑い)
夫は「わかっていないねえ」とすぐに決めつけるので、長女とやりあうこともあります。
夫がカッカして娘に言うので、私が間に入ったらいけないとわかっているのですが、「娘の気持ちはこうなのに何でわからないの」と夫に言ってしまうんです。
それをやめないといけませんね。
娘が自分の気持ちを泣きながらでも訴えるのを、私はいいなあと思っています。
5 親は子どもを信頼していればいいんだね
内園浩二さん
親の会に来て15年ぐらいになります。
お話を聞いていて、皆さんの言っていることが自分の歴史で、今日はいっぱいです。
去年の10月まで妻は親の会に来れたんですよね。
ちょうど今頃だったよな、不安定になったのはと思って。
昨年は女房のお袋の喪中はがきを書いて、それからちょっと不安定になったよねと長谷川さんと話したんですけど、まさか今年自分が彼女の喪中はがきを書くとは思わなかったです。
最初は母親の役割もしないといけないし結構大変だなと思ったんですけど、横浜では通勤していたので、いまは家事をする時間を通勤時間だと思えばいいやと切り換えています。
今ではなんとも思わなくなって苦にならなくなったんです。
先ほど勉強が出来るのが1番というのがありましたよね。
私も横浜では会社で人を使う立場にあって、第一線で働く人も見ているんだけれど、勉強が出来る人で頭がいい人ってあまりいないんですよね。頭がいい人っていうのは勉強が出来なくっても、やっぱり頭がいい、それをずっと感じていました。
1ヶ月ぐらい前、息子が頭を抱えて帰ってきたんです。どうしたんだろうと思っていたら、「お父さん、ごめーん」と、見たら金髪なんです(笑い)。
染めて帰ってきて子どもは怒られると思ったのでしょうかね。そのときふっと「いいんじゃない、中身は変わりないだろう」って、自然に出てきたんです。
だから、これでいいんだよなって。親の会で15年学ばせてもらっても女房の足元にも及ばないんですけど、そういう言葉が自然に出るようになって、最近気持ちも穏やかになっています。
昨日は久しぶりに散歩していたら、ピザーラのバイクが脇をスーッと通って行ったんですけど、それが息子だったんです(笑い)。
俺は今日は散歩をしているのに、息子は一生懸命働くよな、朝も早くから夜10時ごろまで働いて帰ってくるんです。
息子は高校も辞め、どうするのかなと思っていたら通信制高校に手続きしていました。息子は小、中学校に行っていないので、分からないのは分からないんですよね。
でも、友達がいっぱいいるものですから、数学は彼の所、国語は誰のところ、家庭科は女の子がいないので、長谷川さんのところに行って裁縫してもらってと(笑い)、そんな調子でやっています。やさしい子です。妻は亡くなったけど、家族皆で支えあっています。
親の会の10周年、15周年と夫婦で原稿を書いていましたが、たまたま10周年の冊子を今度20歳になる次女が最初から最後まで読んだんでしょう。
次女が8歳の頃、長女が片方の目を失明しましたので、何が原因で、なぜ不登校したのかというのを妻が書いた文章を読んで、「初めて知った事実もある。お父さんとお母さんは大変だったんだね」と言ってくれました。
それで記録に残しておくことってすごいことだよなと思いました。すごいうれしかったです。
そんなこともあって、次女に「親の会に一緒に行こうか」と言うと、「うん」と言うんですけど、しばらくして「親の会に行くと、みんながお母さんに見えるのでちょっと行けない」と言うんです。
だから、学校に行っていないとか、暴力があるとかじゃなくて、親が子どもを認めて、信頼していれば必ず実が帰ってくる、そんな気がしています。
6 子どもは自分で解決できる力をもっている
内沢 達
少し長めに話させていただきます。
Sさんの息子さんが言う「俺が不登校になって引きこもってよかったことはほとんどない」という言葉は確かに否定的です。
「俺なんか生きていてもしょうがない」と毎日のように繰り返し言うのも、いっそう否定的でしょう。確かに、言葉どおりに本人が思っているのは、何割かはそうだと思います。
でも、そうではない気持ちも同じく何割かはあるから、そう言うんです。
前から申し上げていますけど、子どもの発する言葉を額面どおりに受けとめてはいけないことが少なくありません。
さっきのHさんの息子さんの場合もそうで、親をつかまえて「お前!」などと好き勝手なことを言います。他人が聞くと「なんという息子さんだ」と思われるかもしれませんが、いや、親にそういう口調で話せるということは、そう悪いことではなく、親子がいい関係になっているあらわれでもあるんです。
僕自身のことについては前からお話していますし、書いてもいますが、かつてまだ40前だった僕は、小1の娘から「くそジジイ!」と言われました。
僕はこのとき勝ったと思いましたね(笑い)。
この間、妻のほうにいつもメールをくださる方なのですが、遠く千葉から一度鹿児島の例会にまで参加された方ですが、中学生の次男からとうとう「くそババア!」と言われたそうです。
とってもかわいらしい、若いお母さんです。
それを聞いて、かなりイイ関係になってきたなあと思いました。
子どもはある時期「お前」とか「ジジイ」とか「ババア」とか言うものです。
親に遠慮があると言えることではありません。うわべとは違って決して親を否定していません。
Sさんの息子さんが「俺が不登校になって引きこもってよかったことと言えば、お前たちの生活を豊かにしたことくらいだ」と言ったそうです。
これはスゴイですね。息子さんが引きこもるようになってしばらくしてから、Sさんはご夫婦でよく旅行などに出かけるようになりました。
その両親のありようを息子さんは喜んでいるわけです。
自分のことを否定ばかりしているようでいて、じつはそうではない。
両親がとても仲良くなってきた。そうなるうえで、自分の存在も大きかったのではないか、捨てたもんじゃないと言っているわけです。
でも、そうした口に出した部分だけでなく、口には出さなくても「俺って案外これでいいんじゃないかな」とも思っているから、親には安心して否定的なことも口にするわけです。
だから、子どもが否定的なことを口にしたからといって、その通り否定的に受けとめてはいけないんですね。
無意識のうちに、「今の自分でもいいかもしれない」という気持ちを自分のなかで確認し、親にわかってもらいたいという期待がそこにあるわけです。
僕らの会は子どもをどうにかしようという会ではありません。
子どもが悩んでいる、苦しんでいるときに、親が力を貸し援助の手を差しのべるのは当たり前だと思われるかもしれませんが、その考え方を根本から再検討していただきたいと思うんですね。
子どもは自分で解決していく力を持っています。その力を削がないでほしい。
もし自分が子どもの立場だったら、他人からはもちろんのこと、親からであれ、兄弟からであれ、そうされることは心地いいのかどうか、ということを基準にして考えてほしいと思います。
これは、不登校や引きこもりなど、子どもがそうなったことはしょうがないからあきらめて次を考えようということではありません。
親は勝手なもので、子どもの不登校もいよいよ本格的になると、もう学校には行かなくていいから家で勉強してくれないかとか、また引きこもって自分を責めだして元気がなくなってくると、もう勉強はどうでもいいから健康で元気だけはあってほしいとか、じつに身勝手に次を考えようとするんですね。
でも、「今、現在を否定して次を考えようとしても絶対にうまくいかない」というのが鹿児島の「親の会」16年の経験からはっきりと言えることです。
子どもにとっても親にとっても、表面を見ただけでは否定的にしかとらえられない「今現在の状況を肯定できるかどうか」ということが一番大事なことです。
そのことは僕の病気についても言えます。今回の僕の病気と不登校や引きこもりは、もちろん同じにはできませんが、僕自身の課題がどこにあるのかという点では、やっぱり「今、現在の状況を認める」という点で共通しています。
病人が今現在の自分の状況、つまり病状を認めるのは当たり前じゃないか、と思われるかもしれませんが、僕は入院・手術後しばらくそのあたり前のことを認めることができませんでした。
手術後一週間ほどして妻から自分が相当に危なかったことを知らされショックでした。
手術前、入院はしているのですが、どんどん悪くなっていって、痛みや息苦しさ、意識が朦朧としてくる感じはわかりますが、大変な病状とは僕自身思わないわけです。
なにしろつい一週間、10日前までの元気いっぱいのイメージしか自分にはありません。
バイパス手術一般の心配(手術死亡率1〜2%など)はあっても、自分自身が危ないとは全然思わなかったわけです(主治医はこんなに病状の悪い人は、年間数百おこなわれる手術のなかでも、数例だと)。
医者もどんどん悪化していく病人本人にそうしたことは言うはずもありません。
妻が生きた心地がしなかったということを僕は後で知るわけです。
手術前にわからなかったことは無理ありませんが、妻から知らされた後もなかなか今現在の自分を認めることができませんでした。
あんなに元気だったのに、今はなんで声が出ないんだ、すぐに息切れするんだ、ベッドで起き上がるだけでもどうしてこんなに大変なんだ・・・といった調子なのです。
これは、子どもや若者が元気で調子が良かったときの自分と比べて、今、現在を否定してしまう心理とそっくりです。
僕の場合は、病気であったり、手術であったり、きっかけがはっきりしていますので、「今、現在を認める」という点は、比較的容易で時間の問題だったとも言えますが、やっぱり共通していると思います。
療養生活も、今現在を認めることができてこそ、いいものになっていくのだと思います。
僕がこうして元気になってきたのも皆さんのおかげで、妻のトモチャンがおればこそです(拍手)。トモちゃんにこの場をお借りして感謝します。(笑い)
ところで、そのトモちゃん、つれあいの僕が生死の境をさまよったものですから無理からぬ面もありますが、今現在、ちょっと血圧が上がったくらいで、「大丈夫? 大丈夫?」とものすごく心配するんです。
これって、僕は困ります。そういう感じで迫られると、僕は気をつけて調子が良くなるかというと反対で、ますます血圧が上がってきます。
子どもや若者の場合も同じじゃないでしょうか。
親が子どものことを案じて「心配だ、心配だ」といった感じで接すると、子どもはその心配にこたえて「しっかりしよう」「頑張ろう」とするでしょうか。
反対に、しないのではないでしょうか。
たとえしようと思ってもできません。自分自身をなかなか認めることができないところに加えて、さらに「親にまでこんなに心配をかけている自分はだめだ」と自己否定をいっそう強めることになります。
僕の場合は、年齢が年齢ですし、心臓病ですので、血圧やコレステロール、食事、睡眠、運動のことなど、気をつけなければいけないことが山ほどあります。
しかし、子どもや若者の場合、そうしたことはほとんどありません。
親として気をつけなければいけないことは、おいしいご飯をつくってあげることくらいです。その先は、ご飯をちゃんと食べてくれるかどうかだって、心配しなくていいことです。
僕の病状のように大人にも言えるのですが、子どもの今、現在を親が否定的に見るようではいけません。
そもそもからして、登校拒否や引きこもりは明るい話で、辛く苦しいものではありません。
それは、自分が自分の人生の主人公として生きていくことに気づかされる新しい出会いです。
人生は50年時代から80年時代に変わってきています。
人生は短いより、長いほうがいいでしょう。
昔の50年時代なら、僕はもう死んでいましたし、今回のような病気になることもなかったわけです。
病気にはならないことにこしたことはありませんが、病気になったからこそ気づくことも少なくありません。
いまは療養中ということもありますが、かつてなくゆっくりと毎日を送っています。
完全にということはなくても、相当に体力が回復するであろう半年後や1年後も、以前と比べるとはるかにゆったりとした人生を送っているように思います。
不登校の子どもや若者の場合も同じことが言えると思います。
昔の50年時代だと余裕がなく、ゆっくりとできませんでした。
どこの家も貧しく、そのうえ兄弟も多かったので、早く独り立ちが求められました。
自分の人生なのに、周りに合わすばかりの人生でした。
それが今ではどうでしょう。豊かさは隔絶の感があります。
子どもの一人や二人、20代であっても30代であっても、ご飯を食べさせることはどうっていうことありません。
人生は長くなってきているので、昔と比べると試行錯誤ができる幅もぐーんと広がってきています。
人生が長くなってきているということは、時間が増えてきたということです。一日の時間は変わらなくても、生活にゆとりが出てくると考える時間が増えてきます。
そのとき人間というのは、考えなくてもいいことまでいろいろと考えてしまいます。
若者だと年頃ですので、自分の容姿が気になっちゃう。
背が低いの、足が短いの・・・というように。
そういえば僕の場合は、高校時代に自分のひざ小僧の不恰好さが気になってしょうがなかった。気にしなければいけないことではないのに、本人は気になってしょうがない。
子どもがときに不安を口にするのは、そういう背景です。
時間があると、つい、いろいろと考えてしまいます。それだけの話です。
親がいちいち心配するようなことでは、もちろんありません。
そういえば、僕も入院中、することがなくボーっとして病室の天井ばかりながめていると、天井のちょっとした汚れなどがいろいろなものに見えてきて、トモちゃんは「たっちゃんはアタマがおかしくなったのでは?」と真面目に心配してくれた時期もありました。
幻覚や妄想が僕にあらわれたということは、それだけ病気と手術が大変だったということで、僕が正常であることの証明でもあります。
子どもの場合も同じです。大変なときには、大変な状況をあらわしてくれます。
それは、子どもの健全さの証明です。
それにしても、Sさんの息子さんが「俺が引きこもってよかったことはお前たちを幸せにしたことだけだ」と言ったことは、やっぱりスゴイですね。
Sさんご夫婦は、いま人生をいっぱい楽しんでいらっしゃいます。先日は映画「三丁目の夕日」をご覧になったそうです。
9月の例会の後は、佐賀の唐津へ旅されたとか。でもまだ1泊ですね(笑い)。それじゃあまだまだです。
まだどこかに、2泊、3泊以上になると子どもが心配だという意識があるのかもしれません。
それでは、子どもたちに失礼だと僕は思います。
息子さん、娘さんを信頼して、2泊どころか、3泊、4泊の旅行にも出かけるということが、Sさんご夫婦の課題だと思います。
僕らの親の会は、子どものことは子ども自身が自分で道を開いていく、という当たり前の考え方をとっています。
親が、うちの子は問題ない、誰だって悩むときがある、苦しいとき辛いとき、それをわかりやすく表してくれているだけだ、と自然に考えられるようになったとき、そしてそのことを親自身が行動であらわすことができるようになったとき、子どもにも良い影響がでてくるように思います。
「このところ、うちのお父さん、お母さんはえらく楽しんでいるなぁー。
僕(私)のことなんか、何も心配していない!」。子どもから見て、そんな感じになれるかどうかです。
子ども自身が答えを出していくんですが、その大きなきっかけを親が出していくということなんです。
ご夫婦でない場合であっても、父親、母親それぞれが、親としてというよりも、一人の人間として、自分の人生をいっぱいに楽しまれる。
ですから、Hさんの場合も息子さんの更生のためにも、Hさん自身がもっともっとわがままになっていくということが課題のように思います。
|