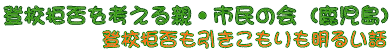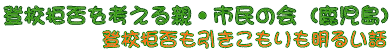体験談
2006年3月発行ニュースより。
登校拒否を考える親・市民の会(鹿児島)会報NO.120
登校拒否を考える親・市民の会(鹿児島)では、
毎月の例会の様子をニュースとして、毎月一回発行しています。
その中から毎月2割から3割程度をHPに載せています。
体験談(親の会ニュース)目次はこちら→
不安は不安のままに、
あるがままを受け入れる
2月例会では、私、内沢朋子が不安をハカリの重さに例えて、話をしました。
わが子が不安を訴えているときに、心配のまなざしで見ることは、いっそうその子の不安が増すことなんですね。2月の例会では、「不安」について話し合い、深まったと思います。
初めて参加された方に、「大丈夫だよ。我が家も同じだった・・・」という「先輩」の言葉は暖かいですね。
福岡から初参加のめんたいこさんはHPに、〈子どもを愛して、「何もしない」でいよう。
そして私自身も「あるがまま」で子どもに接していこう・・・〉と例会参加の感想を寄せています。
昨秋から始まった離婚裁判を契機に不安がなくなっていったというEさん、月日が経つにつれて「わが子は親の私よりしっかりしてるんじゃないか」と感じたというCさん、信頼しあえるからケンカもできる、いつしか娘に支えられていると気がついたというGさん、わが子にメールや手紙で親の溢れる愛を伝えたというまつこさん、親の会に参加して自身の不安やあせりがなくなったというMさん、本音で話すことができるのは自分の母と親の会だとわが子に堂々と言っています、というKさん、娘の弁当が何より楽しみ、娘たちの生きかたは私の自信です、というNさん、例会に参加するうちに不安がとれ、元気をもらってきたというYさん・・・。たどってきた道を見ると、いつしか幸せになっている、穏やかになっている、と気がつくのですね。
「計らいをすてる」「あるがままの無条件の愛」の大切さです。
押し寄せる不安を不安のままで、あるがままに受け入れる、そのことを繰り返し、繰り返し親の会で学んでいきましょう。
内沢達は自分の病気の体験から不安について話しています。
最後にいじめでわが子を亡くした村方敏孝さんの言葉は重く、熱く参加者の胸を打ちました。
1 自分の人生を大切に生きていこう Eさん
2 わが子の状態が不安で・・・ Uさん
3 不安は不安のままで 内沢朋子
4 高校中退し、何度も県外で働こうとするが・・・
5 僕も「不安神経症」に・・・ 内沢 達
6 ひょっとしたら、息子は親の私よりしっかりしてる・・・
Cさん
7 娘に「追いつめてしまって、ごめん」と書き綴った日々
まつこさん
8 娘たちの生き方は、僕の自信です Nさん
9 わが子を亡くして10年の月日 村方敏孝さん
1 自分の人生を大切に生きていこう Eさん
―――Eさんは息子さんが3人いらして、25歳の次男さんが高校中退で、今大学に行って3年目だけどほとんど行ってなくて、21歳の三男さんは通信制高校に在籍しています。
ご自身が夫と5年前から別居していて、今は離婚の裁判中ですね。
5年前に離婚の調停と不登校が重なって、ものすごくパニックになって自分自身が引きこもってしまう状態になって、あの時はほんとに大変で不安でいっぱいでした。昨年の10月に離婚の裁判を言われたときもすごく落ち込んでいたけど、早い時間で回復しましたね。
はい、前のときは穏やかになるまで5年かかったんですけど、別居してその間は婚姻費用分担請求をして生活費は入ってきていました。
いよいよ夫は生活費をやりたくなくなって訴訟を起こしました。今、裁判中なんです。
私は答弁書を書き、過去のことを全部書いたら、そのときのことを思い出して以前と同じように不安が押しよせてきました。
でも今度はすぐ穏やかな状態に戻りました。
三男も同じように不安になりましたが、今穏やかに暮らしています。
―――よかったですね。今度はどうして短期間のうちに穏やかになれたんですか?
親の会では皆さん優しくていい人ばかりで、ここでは同じような悩みを持ってる人たちだから皆優しいと思うんです。でも、裁判となると今度は違う人たちと接することになります。
裁判官、弁護士、書記官、登記関係の方たちにわからないことをいろいろ聞くと、皆さんが丁寧に教えてくれるし、書記官さんも弁護士さんもすごくいい人で、親の会以外でもいい人たちがいるんだと実感したからだと思います。
知り合いなどにも「裁判中なんですよ」と言うと、「大変ね」、「頑張ってね」とか、80歳くらいの方が「私に何か出来ることはないの」と言ってくれたり、皆さんが色々と言ってくれて、それがエネルギーになっているんだと思います。
―――あなたは人が怖くなくなってきたんですね。
この5年間引きこもっていてエネルギーがいっぱい溜まってきたのね。
はい、だんだん怖くなくなって。ほんとは今大変な状況なんで、まだ引きこもりですが、息子たちと穏やかに暮らしていて、なんか楽しいです。
―――弁護士さんにも「引きこもり」というのはこういう事なんですよと教えたりしてね。
はい、弁護士さんに「今度は5年かからないで元気になりました。すごいでしょう」と言ったら、顔を真っ赤にして笑って、「引きこもりと言われるけどそんなふうに見えませんね」と言われました。
それで引きこもりについて私のいくつかの例を出してお話しました。
私も次男も引きこもりをしているので、次男が外が怖いから私に、「これを買ってきて」と言うと、私も「怖いから出たくない」と言って、次男が「しゃーないな、俺がついて行ってやる」と言って二人で買い物に出かけたり、こっちの道が怖いからあっちの道を行くんですと、他にも色々話して、「引きこもりって面白いでしょう」と言うと、びっくりされていました。
車の運転も、裁判の呼び出しがあってからは鹿児島市内まで怖かったのですが、「今まで車でこれなかったけれど、今日は運転してきました」と言うと、「そうやってひとつひとつ自信をつけていけばいいんですね、お帰りは気をつけて帰ってくださいね」と言われました。
弁護士さんが私の辛い気持ちをわかって下さるので、私はとても安心できるようになったんです。
―――人の親切も思いがけないことで感じることができますね。それは、自分の人生を生きていこうという姿勢がまわりの皆さんに伝わるからでしょう。
大人であっても不安になるのは誰でも起こりうることで、でも見方を変えればこういう体験を通して自分を肯定していくことができるんですね。
2 わが子の状態が不安で不安で・・・ Uさん
(―――今23歳の長男さんが不登校の後、家にいて、17歳の三男さんが食事ができなくなり、お話しなくなって、今は三男さんのことが心配で心配でたまらないのですね)
はい。心療内科に連れて行ってはいけないとは思いつつ、親として何かしてやらなければと不安にかられました。
それで、先月は、心療内科に連れて行ってみようと思いながら例会に参加したら、ほんとにたくさんその話が出て、行かなくて良かったと確信がもてました。
どんなことがあっても心配しないで放っておこうと思っていたんですが、先週の日曜日に風邪から熱発して近くの病院に連れて行きました。
口内炎が出来て喉が痛いと紙に書いて、起きてるときはしゃっくりみたいな咳がずっと出ていたんです。寝ているときは全然出ません。
痩せてるので、その咳を聞くたびに私は可愛そうで苦痛でした。
胸が痛い、お腹も痛いと書いて訴えるし、そのうえ1週間もお茶しか飲めなくなりフラフラしながら私たちが出かけるとついてくるのです。
睡眠も不足がちでいつまでも寝ないでいるので4時半頃「早く寝なさい」と言ったら、立ち上がった拍子にフラフラして冷蔵庫にぶつかって気を失ってしまったんです。
私は思わず引きつけたと思って、長男に「早く救急車を!」とパニックになったんです。
引きつけの薬も飲んでいなかったし、引きつけたと思ってしまって。
―――持病だった引きつけだと思われたのね(はい) 最後の引きつけはいつだったの? (幼稚園の卒園式です) そのときに医者に脅されて・・・(はい、今度引きつけたら脳に障害が残るみたいなことを言われたんです。発熱したときしか引きつけないのですが、たまたま薬を忘れたときに引きつけたので、この薬が命の元だとずっと思っていたのです)
入学前といったら6歳くらいでしょう。10年間も何も起きてないのに、それがインプットされて、「脳に障害が、脳に障害が」と、飲ませ続けたんですね。
倒れたときは死ぬときだと思い込んでいたので、死ぬかもしれないとパニックになったんですが、心臓が動いていたし、10分もしないうちに意識が戻ったんです。
救急車で市立病院に行って、CTや胸の写真を撮ったんですけど、異常はありませんでした。食べてないので点滴くらいしてくれるかなと思ったんですが、そのまま帰されました。食事が摂れてないことや口をきかないことを脳神経外科の先生に話しても、精神科でないと入院は出来ないと言われました。
(―――その後またNクリニックに行かれたの?)はい、親の会で散々言われたんですけど、カウンセラーが知り合いの方でしたので相談したかったのです。しゃっくりみたいな咳は「チック症」だと言われて、「統合失調症」だと診断され、一番は入院がいいと言われました。
さらに別のかかりつけの先生に私だけ相談に行ったところも入院を勧められました。「行きたくないという子どもをどうやって連れて行くんですか」と聞いたところ、「精神科だったら迎えが来て、無理やり連れていくことができます」と言われて、そんなことを初めて知りました。
そうなったとき、「息子の気持ちに反して連れて行くということは、もっと子どもを傷つけることになるのではないですか」と尋ねると、「それは長く経って完治したときに、僕のためにお母さんが入院させたんだなとわかる」と言われたんです。
個室に入れられるそうで、何をされるかわからないし、絶対入れたくないと思いました。
私は普通に入院して栄養剤の点滴をしてもらいたいと思っていたので、その話を家族みんなにしたら反対しました。やっぱりそうだと思って内沢さんに電話しました。
今日も筆談で「頭の中が痛い」と書いたので、「あっ、そう」と言って放っています。たまたま次男が春休みで帰省してきたら、ゆっくり寝ることが出来て落ち着いてきました。
三男が、最初食べられなくなったのは一昨年の9月くらいからで、言葉が出なくなったのは昨年の1月からです。
3 不安は不安のままで 内沢朋子
(上のUさんの発言に続けて)
―――私たちはおかしいと思ってないんですが、例えばわが子が、拒食・過食だったり、家庭内暴力だったり、言葉の暴力、脅迫行動、閉じこもりなどなど、いろいろあるわけですね。不登校から発していろいろ出てくるでしょう。
でもこれは不安なんですね。もしここに不安を量るハカリがあるとしましょう。自分が異常ではないか、とそればっかりを考えてしまうと、そうするとどんどん不安が増していって、ハカリの目盛りがグーンと重くなっていきます。
例えば、拒食・過食はあれを食べよう、これを食べよう、食べられない自分はだめだと、食べ物のことばっかり考えているわけです。
言葉が出ないと言葉のことばかり考えている。そうやってどんどん人は不安が拡大していくんです。ものすごい勢いで不安を拡大して再生産していきます。
特にこのままでは将来が不安だ、とほとんど恐怖になっていきます。
そのことばかり考えて不安というものを形作っていく、それは誰でもなるんですね。
そのときに親がもう食べられないの、言葉が出ないの、暴力が、閉じこもってとか、学校に行くだろうか行かないだろうかと、そのことばっかり考えている子に、そのことばっかりに関心を寄せて、心配で心配でたまらないと言う。
言わなくても心配の眼差しでオロオロする。そうしたら当事者はどうなりますか。心配で心配でたまらないと言われたら、この不安はもっと太って大きくなっていきます。
昨日、Tさんからのメールで、風邪気味のときに職場の皆さんから大丈夫ですか、お手伝いしましょうかと言われてしまい、心配されるのはありがたいけれど、放っといてほしいと思ったと、我が息子の放っといてほしいという気持ちとだぶったと書いてありました。
このことで、私も思い出しました。まだ10代で初々しく恥らうころですよ。
冬の北海道のバスは床が凍っている時代で、そこにクリスマスケーキを2個持ってバスの後部から歩いて来た私は、皆の座っている前でズテーンと転んだんです。
そのときくらい恥ずかしかったことはなかったんですよ。(笑い)
放っておいてもらいたい、見ない振りしてもらいたい、と思っているのに、大丈夫ですか、痛くないですか、とそんなこと言ってほしくないんです。(笑い)
いろいろ言ってほしくないと思う、そういう心理です。
心配の眼差しでどうなの、どうなのと24時間見られている、もうどうかなったんじゃないかと思われる、これくらい当事者にとって負担なことはないんです。しかもそれを一番親がするんです。
親はどうしたらいいのか。不安は不安のままでいいじゃないのということです。これが「あるがまま」です。これはとっても大事な言葉だと思うんです。
あるがままを受け入れる、不安は不安でいい。何とか治そうとする考えを捨てなさいということです。治そう治そうと考えるから、心配だ心配だとなっていくんです。
子どもに対して、あるいは子どもに限らず連れあいに対して、家族はどうするのか。「信頼する」ということです。その子のあるがままを、我が夫の、我が妻の、我が家族の生きる姿をそのままを受け入れるということが「信頼」ですね。
この間の私たち夫婦の体験でも大事なことだと改めて思いました。夫が心筋梗塞になり大きなストレスを抱えたわけです。
今まで順調に回復してきましたが1月中旬、突然呼吸が困難になって歩けなくなり、血圧も上がってくる。大きなストレスの中で体がそういうふうになっていったんですね。
私はそれが不安からくるものだと知ったとき、とても安心しました。
その状況のあるがままの我が夫の姿を受け入れる、それが夫、達のあるがままなんだよということを心から受け入れる。それが信頼をするということです。
信頼の土台は何かと言うと、「無条件の愛」です。愛がなかったらできないでしょう。心配する愛は条件付き愛です。拒食を治したら安心、暴力がなくなったら安心、親を困らせなくなったら安心、このハカリの目盛りを軽くするならばそのままの状態を受け入れるということです。放ったらかすということでしょう。そのままで受け入れるということは、全然心配がなくなってくるということです。「計らい(はからい)を捨てる」ということです。
そのままあるがままの姿で受け入れてください。
あなたの不安がなくなれば、あなたが不安で不安でたまらないという気持ちがなくなれば、必ず息子さんの不安は小さくなっていきます。あるがままを受け入れてくださいね。
4 高校中退し、 何度も県外で働こうとするが・・・
(高校中退したあと、何度も家を出て県外で働こうとするが、うまくいかず苦しむ息子。
人が怖くなり、自分は病気じゃないかと思ってしまう。でも、家には帰りたくない、という・・・)
―――「これじゃダメだ、これじゃダメだ」と息子さんは思うんですね。ちゃんとやろうと思っているのに、なんでダメなんだろうと更に自分を追い込んでいくのです。
家には帰りたくないと言って、同じパターンを山口、北海道、今度は大阪で4ヶ月と繰り返せば繰り返すほど、自分は働けないと思い、人が怖いという意識が集中してしまいます。
人と話が出来ないので小旅行をして人と話せるようにと自己暗示をかけたり、訓練しようとします。「働けない」「人が怖い」ということに不安が集中していくので、生活できなくなっていくのです。
でもその時に帰るべきは我が家族のところなんです。我が家族には無条件にその子を受け入れる愛情があるんです。
「ブラブラ遊んでいて、なにもしていない」と世間は言うかもしれないけれど、その時に「大きく回り道をしても自分らしく生きようと考えているんだ」と家族がよく理解して、「お兄ちゃん、よく帰ってきたね。一緒に暮らそう、家族だもの」という雰囲気があれば俺の居場所がないとはなりません。
しかしそういう雰囲気があったとしてもすごく自分を責めます。
大きくなればなるほど責めます。働くことが人生の最大の目標だと追い込んで自分自身を縛るんですね。
「働く」ということは人生最大の目標ではないんです。
人生最大の目標はその人が幸せだと実感することですね。自分は本当に幸せだと実感できることなんです。
―――(内沢達):息子さんが帰ってくることについて、お母さんご自身の気持ちを話されたらいいんですよ。もちろん迷われていると思いますけどね。
何とか大阪でやっていけないかなという気持ちもあるし、だけど難しいのではないかという気持ちもありますよね。
もし難しいのではないかという気持ちのほうが大きいようでしたら息子さんに、「あなたは戻ってきたほうがいい」ではなく、「お母さんは(あなたに)戻ってきてもらいたい!」「(あなたが)戻ってくれたらウレシイ!」と伝えて下さい。
「あなたは・・・」という言い方では、息子さんに自分を責め続ける材料が増えます。
「お母さんは・・・」と言うと、「ああ、お母さんの気持ちはそうなのか」と自分自身のことを少し距離を置いて考えられるようになります。
これは、お母さんがお母さん自身の気持ちについて述べたことですので、息子さんが自分を責めなくてすみます。言い方としては、「あなたは」という二人称ではなく、「お母さんは」と一人称で言うことが大事なんですね。
もうひとつは仕送りをしないということです。
お母さんが「戻ってきて欲しい」と言っても、息子さんは簡単にはOKせず、きっと「いや、俺はもう少しがんばる」と言うでしょう。
途中で帰るのはかっこう悪いから、帰れないと思っています。
今までも2回そういうことがあって今度こそと思って出て行っているわけですから、とてもじゃないけどかっこう悪くて帰れない。
それではどうやって帰るきっかけを作るかというと、それは仕送りをしないことです。経済的に向こうでの暮らしが成り立たなくなると帰るほかありません。
御両親の判断で仕送りをストップすることです。仕送りがあるから、すでに頑張れる状況でないにもかかわらず、「いや、頑張る」「頑張らねば・・・」と思って、でも、それができない自分を責め続けてしまうことになります。
親の会への参加はまだ2回目で戸惑われていらっしゃるかもしれません。
普通世間では会話やコミュニケーションで子どもを励まし、仕送りなど経済的な支援をおこなうことが親の努めのように考えられていますが、私たちは違います。
親子の関係がうまくいかないのは、たいがい親が何かをしないからではなく、何かをしちゃっているからです。
子どもを励まそうなんて思わないで、親は自分自身の気持ちを素直に話したらいいんですね。仕送りも、することよりも「しない」ことのほうがよほど支援になる場合が少なくありません。
(息子は「帰れば仕事は絶対にしない。
またケンカになるし、妹たちにも当たるよ」と言うんです。そう言われると私も夫も何も言えなくなってしまいます。親の気持ちを読み取っています。)
―――(内沢達):息子さんがそう言うのは反対に、本当は家に帰りたいと思っている証拠ですね。「仕事をしなくていいのか、妹たちに当たったり、ケンカをしてもいいのか」と、その具体的な答えを期待して言っているわけではありません。
「そんなダメな自分でも認めてくれるのか」ということが息子さんの一番の問い、願いです。だから、それらには「いいよ。そうだよ。お父さん、お母さんが近くにいるから安心だし、お父さん、お母さんもお前がそばにいてくれたら、とてもウレシイ!」と答えたらいいんです。
5 僕も「不安神経症」に・・・ 内沢 達
―――(内沢達):息子さんはテレビを見て自分も同じ病気ではないかと思ったんでしょう。
でも、それは病気じゃありません。
僕は昨秋心臓を手術して大変な思いをしたけれど、この1ヶ月間とてもいい経験をしました。
この間に僕の病名が1つ増えました。1月末のことです。
かかりつけのクリニックで、横から見てると医者がカルテに「不安神経症」と書き込んだんですよ。
高血圧や狭心症・心筋梗塞という本来の病気にプラス、不安神経症となりました。でも、これも病気じゃありません。
僕は昨年10月末に退院して11月、12月、そして新年1月の10日すぎまではずっと順調でした。その間調子が悪くなるのはホームページの更新がうまく出来ないとか、大学でのこととか、必ず思い当たる原因がありました。
そして調子が悪いといっても1日か2日でした。
ところが、1月10日すぎから4週間ほど、ずっと具合が悪かったのです。
すぐ息切れがしてしまうんです。
血圧は高くなく落ちついているのに、ちょっと歩くと呼吸が浅く「ハァーハァー」と息切れしてしまうんです。
先月(1月)の親の会でも、参加された方はお気づきと思いますが、僕は途中で何度か「ハァーハァー」と休みながら話していました。
今日ここまで自宅から徒歩で来たのですが、その歩きが大変でした。
前だと自宅から大学まで片道3キロを往復しても何ともないくらいに元気で順調だったのに、1月中旬から50メートル歩くのも大変になりました。
クリニックで負荷心電図をとってもらったところ、6、7分の間に3回も不整脈がでて気分が悪くなりました。
その翌日のことですが夕食後「ハァーハァー」とものすごく呼吸が速くなり、血圧も上がってきました。妻が電話連絡をとったところ、医者は「心電図をとれるように、すぐにも救急車で入院を」とすすめましたが、間もなく落ちついてきたので、僕は「明日一番に先生のところで診ていただいてから」と答えました。
でも、夜中にまたおかしくなり血圧も上が180を超えるほどでしたので、119番で救急車を呼び緊急入院しました。
そんなことを聞くと「たっちゃん、大丈夫なの?!」と心配されるかもしれませんが、まったくどこも悪くないということが段々本人にもわかっていきます。
かかりつけのクリニックの医者は深夜なのに病院まで駆けつけてくれて、「心電図その他まったく異常なし!」と妻や僕に笑って帰っていくほどでした。
入院といってもたった一泊でしたし、翌週、医者から「ウチザワさんはメンタル面でちょっと・・・」ということで、「不安神経症」というありがたい診断をもらったわけです。(笑い)
どうして僕が呼吸も速くなって息切れがしてやがては血圧も上がってきたかというと、すべては身体的な異常からではなく、精神的な不安から起こったことです。
僕は昨秋倒れて、心臓バイパス手術の後、しばらくは知りませんでしたが、相当に危なかったようです。
手術直後、主治医は妻に僕が助かるかどうか「五分五分」と言ったそうです。「危ない、ひょっとしたら・・・」という恐怖が僕にはずっとあるんですね。
この間、かかりつけの医者は、血液検査や心エコー、心電図の結果から「どんどん良くなって回復してきています。心配ありません」と太鼓判を押してくれています。
僕はそのことを頭では了解しているのですが、気持ちでは納得していないんです。
「良くなっているんだったら、なんでこんなに息切れがするんだ?」「どうして歩けなくなったんだ?」「入院中だって、もっと歩けた!」「いまではホームページの更新がうまくできないからといって、いらいらはしない。なのに、どうして血圧が高いんだ?!」「職場のこともうまくいっているのにおかしい?」などと、どんどん疑問が出てきます。
つまるところは「どこか悪いところがあるんじゃないか?」という漠然とした心配や不安です。
でも、こうした不安は僕に限ったものでないことが分かってきました。
今から、80年も昔、昭和の初め、1920年代の本なのですが、慈恵医科大学精神科教授の森田正馬(もりたしょうま)が心臓神経症といって、僕にもぴったりの例を紹介しています。
心臓自体が悪いわけでないのに、それを疑って注意を集中すればするほど、心悸亢進(しんきこうしん)が起こってきます。
横隔膜がせり上がって呼吸が浅く早くなってきます。
心臓のことを「心の臓器」とはよく言ったもので、身体であっても心のありようと切っても切り離せません。器質的にはなんの問題がなくても、心のありよう次第では、素人から病気を疑われるような身体の状態になってしまいます。
不登校や引きこもりの子どもは、概してヒマで時間がいっぱいあります。そこで、考えなくていいことまでいろいろと考えてしまいます。
僕もいまはかなりヒマです。(笑い)
30年近く勤めてきて、初めてもらった休暇のような面もあり、時間があるものですからついよけいなことを考えてしまいます。「どこか悪いところがあるんだ!」と。
そうすると身体がおかしくなるんですね。これはおかしいと思うからおかしくなるんです。
みなさん、暗がりで自分の歩く音に驚いたことはありませんか。僕の大学の研究室は4階にあって、古い建物ですので足元を照らす非常灯もなく、深夜真っ暗な階段や廊下を歩くとき、変な想像を働かせると怖くなります。
そして急いで建物の外に出ようとする自分の足音にまた怖くなります。(笑い)
森田正馬は、不安や恐怖は誰にでもあることで、その「あるがまま」を受け入れよと言っています。僕の場合だと、「ハァーハァー」と過呼吸が始まったら、それをおかしなこととは考えないで、なるがままにまかせよということになります。
過呼吸のようなことをなくそう、なくそうと考えると逆に「ハァーハァー」はいつまでも続きます。これを自然なことと受け入れたとき、なんとなくなっていくということになります。
2月に入ってから一度、少し強めの発作がありました。
また「ハァーハァー」と呼吸が速くなり、血圧が相当上がりました。「今度具合が悪くなったらこれを飲みなさい」と言われ処方されていた精神安定剤を飲んでもよくなりません。
(「えっ、たっちゃんが飲んだのですか?」「ええ、飲みました」。笑い)そこで医者にトモちゃんから電話してもらいました。医者は「ニトロをなめさせ、放っておいてください」と言ったそうです。
ニトロをなめるとじき落ちつきました。不思議ですね。
ニトロは狭心症の薬、血管拡張剤です。血管の狭さくはないので関係ないはずなのですが、精神安定剤は効かないのに、ニトロだと効く。
すべては心のありようで説明がつきます。
昨秋、心筋梗塞で倒れたとき、その痛み、苦しみをニトロが即効的に軽減してくれた、ニトロがまず第一段階で僕の命を救ってくれたという、この薬への信頼感が他と全然違います。
また医者が僕を放っておいてくれたことが大きいんですね。
森田正馬は、神経症について「これを病気として治療しようとしてもけっして治らないが、ただこれを普通の健康者としてとりあつかえば容易に治るものである」と言っています。
誰しも人前で緊張して赤くなったり、声が震えたり、心臓の鼓動が激しくなったりするという経験が多かれ少なかれあります。それにとらわれすぎると病気のようになっていくのですが、それは病気じゃありません。
僕の場合も、狭心症や心筋梗塞は病気ですが、「不安神経症」と診断された、この一ヶ月の状態は病気ではないということになります。
この一ヶ月、とてもいい経験をしました。不安から逃れる道はその不安を否定するのではなく、不安をそのまま認めて、不安とともに生きて行けばいいんですね。
6 ひょっとしたら、息子は 親の私よりしっかりしてる・・・
Cさん
―――お久しぶりです。不登校になった息子さんについて、担任が「この子の人生は13歳で止まってしまう」と言ったんですね。
学校に行くと約束させられて、行かなかったら、担任は息子さんに土下座させて謝らせたんですね。ひどい話ですね。
はい。中2の男の子です。今息子は、夜は自分の部屋でトリノオリンピックをずっと見て、朝は下に降りてきて寝て、昼間はずっとパソコンをしているという毎日です。
子どもと話をしていて、小1の時のことを思い出しました。その頃息子は朝6時には登校していました。
「お母さん、小学校は40分の授業の後、なんでたった10分の休みしかないの?」と私に聞いてきました。私は忙しかったこともあって「そんなことお母さんに聞いても分からないよ。先生に聞いたら」と言ったんです。そしたら子どもは「校長先生に電話をして聞いたよ」と言ったんです。返答がどんなものであったか、もう覚えていませんけどね。
先日もやっぱり同じことを言ったんです。
「長い授業の後の休み時間は短いし、遅刻をしたら校庭を走らされたり、なんで罰せられないといけないの」と言いました。
「何で掃除をしないといけないの」とも言ったので、この子は小学校へ入学した頃からずっと学校に不信感を抱いていたんだなと思いました。
私が「でもね、社会へ出たら朝8時までに会社へ行って仕事をしないといけない決まりがあるんだよ」と言ったら、「お母さん、お金がもらえるじゃない。僕はお金をもらえるのだったら頑張るよ」と言ったんです。(笑い)
この子はすごい合理的な考え方ができて、親の私よりひょっとしたらしっかりしているんじゃないかと思い、感心しました。(笑い)
将来、引きこもっている息子が急に外に出て働けるだろうかと思い、夫に話したら「それはちょっと無理だろうね、出たり入ったりしながら壁が厚いという経験を持つのではないか」と言いました。本人は16歳になったら働くと言っています。
「今の小遣いではやっていけないので、しっかりお金を稼ぐから。お母さん、将来僕はお金持ちになるかもしれないよ、将来のことは誰にもわからないから」と言います。(笑い)
―――本当ですね、将来のことは誰も分からないですからね。
親御さんの心配はいらないでしょう。今息子さんが家にいることは、あなたはもう認めていらっしゃるんですか?
そうですね、言えば言うほど事態は悪くなるようで…。今はもう黙って子どもが動き出すのを待つしかないですね。
(―――お父さんはどうですか?) 夫も同じような考え方です。しかし、夫と息子はあまり話をしません。たわいもないテレビのこととかは少し話しますけれど、将来のこととかはお互いあまり話しません。(―――その方がいいですね)
今日も私が親の会へ誘ったのですが、夫は「信じるものは救われるじゃないけど、宗教的なものがあるんじゃないの?」と言いました。(笑い)
私は「いろんな人の話を聞くとまた考えも変わるよ」と言うのですけど、夫も今は子どもに対してどうすることも出来ない感じですね。
私からは息子はしっかりしているように見えるのですけど。
この前も煙草がわざと眼につく机の上に置いてあり、1本だけ吸っているみたいでした。
私はそれも見て見ぬふりをしています。
金髪染めも置いてあり、いつ染めるのだろうか待っていたら染めないで、次に見たら、金髪染めの横に黒髪戻しが置いてありました。(笑い) 心配だから一応買っていたんだなと思って…(笑い)。
―――息子さんとは楽しくお話ができるんですね。(はい) 学校の干渉もなくなって、なりよりですね。あなたの気持ちにあまり不安がなくなってきたんですね。
今は前よりも気持ちが楽になりました。
まさか我が子がこんな風になるなんて思ってもみませんでした。ちょっとパニックになりましたが、ひょっとしたら息子は私が思っていたよりしっかりしているかもしれないと思えるようになってきました。
この間いろんなことがありました。息子の親友が息子の部屋に黙って入って息子の財布からお金を抜き取ったんです。息子はショックを受けました。
その子は自分の家からもお金を取ったりしている子でした。
息子はもう遊ばないかなと思ったら、ちゃんと謝らせて「もう二度と俺の部屋には入れないからな。だけど遊ぶのは遊ぶから」と言っていました。まあ、その子しか遊ぶ相手がいないのだけれど、ちゃんと言っていました。
下の子どもたちが食事中に本を読んだりすると、田舎のお祖父ちゃんみたいにガアーと叱ります。うるさいのです。(笑い)
(―――上のお兄ちゃんだけが行かなくて、下の子どもさんは行っているんですね)
はい。小6と小3の子が時々、「何でお兄ちゃんは行かないの」と言います。今度娘がお兄ちゃんと同じ中学へ進学するものですから、私の母がすごく心配して、「この子も行かなくなるんじゃないか」と言っています。
「親戚に恥ずかしい」とか、「うちの親戚にはこんな子はいない」と言ってくるんです。私は「そんなこと言わないで。下の子は行っているんだから」と言います。
―――(内沢達):お母さん自身は「あなたも休みたかったら休んでいいよ」と弟さんには言えないんですね。「嫌だったらお兄ちゃんみたいに学校を休んでもいいんだよ」とはまだ言えませんか?(う〜ん)(笑い)(なかなかですね。「お兄ちゃんはずるい」と3番目は言います)
お兄ちゃんのことをずるいと言うのなら週に1回でも休ませてあげたらどうですか? それも心配ですか?「お兄ちゃんはずるいのではなく賢いんだよ」と教えてあげたら・・・
親としては複雑なんですよ。上が行かなくなると結構連鎖反応じゃないけど(笑い)、下の子も行かなくなってますよね。やっぱり心配は心配ですね。
―――そうやってお兄ちゃんのことを受け入られるようになってよかったですね。下の子どもさんはまた行かなくなったときに考えましょう。
7 娘に「追いつめてしまって、ごめん」と書き綴った日々 まつこさん
(不登校の息子さんが毎晩のように家を出るという初参加の方の話を受けて)
21歳の娘と17歳の息子がいます。
夫の転勤で娘が中3になったときに転校しました。2学期くらいから五月雨登校になり不登校になったんですが、やはり高校には行かねばならないという気持ちから開陽高校の定時制を受験しました。私もその当時は不登校ということが全くわからなくて、行かせることが娘の人生にとっていいことなんだと考えていました。そういう価値観の中で行かせましたので長くは続きませんでした。
娘は家に居場所がなかったんでしょう。毎日外に出るようになり、夜中に出て行っていつ帰ってくるか心配でたまりませんでした。3日間くらい帰ってこなくて、帰ってきた娘を私は殴ったこともありました。お互いに殴りあったこともありました。そして帰ってくれば、どうだこうだと説教をしていました。
私はすごく心配で、内園由貴代さんに毎日のように相談していました。由貴代さんは、「今子どもが求めているのは受け止めてくれる心なんだよ。友達はその時々で変わっていくから心配しなくても大丈夫。帰ってきたらおいしいものを作って食べさせてあげなさい」とよく言ってくれました。それが心に残って、お母さんはあなたのことが絶対に大事なんだよ、と手紙に書いて伝え続けました。そして私が不安がなくなって落ちついて変わっていったら、自然に娘も帰ってくるようになりました。
その時はどうして娘の気持ちが外に向いてしまうのかわかりませんでしたが、本当は不安で不安でたまらなかったんだなと思います。私は娘にメールや手紙で「お母さんはあなたの気持ちがわからなくて追い詰めてしまった」と心を込めて書き綴りました。
今でも私は娘と一番ケンカをします。ケンカが出来るということはお互いを信頼しているからで、ケンカをしても普通に話せるんです。年月が経って親が落ちつくと子どもはしっかりと考えて行動していきます。親御さんがしっかりこの子は大丈夫だと腹を据えていくといいですね。
8 娘たちの生き方は、僕の自信です Nさん
21歳と17歳の娘二人が不登校です。
今は平穏で、今日は何を話そうかと妻と車の中で話してきたくらいです。
(―――お父さんは娘さんたちから阻害されたことがありましたか?)
それはありませんね。いつもご飯を食べて、特別話をするということはないんですが、テレビを見たり、パソコンをして過ごしています。
(―――それはよかったですね)はい。娘が弁当を作ってくれるんです。愛娘弁当ですかね。(笑い) 妻はしてくれないけれどいい娘でよかったです。(笑い)
以前は私が一方的に押しつけるような叱り方をして、娘は泣いていたんですが、今は1対3でやってくるものですから、私が負けてしまいます。堂々と意見を言って、言っていることが理解できるんです。そして泣きません。妻ともよくけんかをしているので何をしているのと聞くと、自分の言いたいことを言っているんだと言うんです。お互いを認めあっているから、出来るんではないかと思っています。
(―――Nさんは何年前に親の会にいらっしゃいましたか?)平成10年からですから丸7年になります。
(―――気がついてみたら自然に暮らしていらっしゃる)そうですね。最初行かなくなったときには原因を探そうとして、何があったのか、いじめられたのかといろいろ聞こうとしたんですが、絶対に話さないんです。受け入れるまではまさか我が子がという思いがあって時間がかかりましたね。そのショックは今でも覚えています。この会に来る以前も、まあ行かなくてもいいかなと思う気持ちはあっても、やはり心の中では行って欲しいという気持ちが大きかったです。
最初の頃、娘は死んでしまうんではないかと思えるくらい自己否定が強かったです。この会に来てそこまでして行かなくてもいいと親が思えるようになった時に自分達もホッとしたし、娘もホッとしたんだと思います。
下の娘も不登校になり、職場で大丈夫?と話かけてくれるんですが、そう言われてもなんともないというか、それがここで勉強している自信だと思います。(―――ちゃんとそんなふうに落ちついていくんですね。問題だと思うから不自然なのであって、自然に暮らして行けばいいんですね)
9 わが子を亡くして10年の月日
村方敏孝さん
ここに来るようになって10年目になります。長男が親に内緒で学校に行ってないことを知り、それがわかった翌日に私は学校に行きなさいと強く言ってしまいました。そのあと息子は死を選んでしまいました。
生きていれば皆さんと一緒に笑ったり、悩んだりして勉強していると思うんです。生きて私を困らせて欲しかったと思います。今はこの世にはいないけれど、息子への罪ほろぼしのつもりでいつも勉強させてもらっています。生きていればこそといつも思いながら、本当に子どもを追い詰めないことだと思います。私は子どもに、学校に行けと言ったばっかりにこういう結果になりました。
―――1996年9月18日に勝己君はいじめで自殺しました。いっぱい調査をして勝己君の無念を晴らすべく、ご両親は裁判を起こしたんですね。ですから村方さんの言葉は本当に重いんです。HPに村方美智子さんの「かけがえのない我が子を失って」が載っていますのでお読みください。
私はいつも会を始める時に、15歳で命を絶った勝己君のことを思います。子どもを亡くしたということは何よりも耐え難いことだと思います。でも村方さんは御夫婦で支えあって、その御夫婦愛の素晴らしさに私はいつも感動しています。家族で支えあう、家族というのはそれだけでかけがえのないものだと思います。